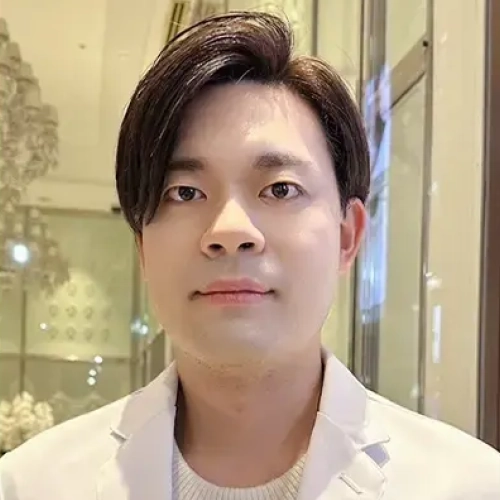魚の目は自己処理で改善できる?原因やケア方法・放っておくとどうなるか解説!

魚の目ができると、自己処理したくなる人もいるでしょう。しかし、魚の目は中にある芯を取り除かなければ改善とは言えないので、自己処理は危険です。この記事では、魚の目ができる原因やケアする方法などについて詳しくご紹介します。
もくじ
魚の目とは?
魚の目とは、足の裏や指の関節部分などにできる、皮膚が硬くなった小さな円形のしこりのことです。正式には「鶏眼(けいがん)」といい、硬くなった角質の中心に芯があるのが特徴です。この芯が皮膚の内側に食い込むため、歩くと痛みを感じることがあります。見た目が魚の目に似ていることから「魚の目」と呼ばれるようになりました。
足の裏や指の側面など、圧力がかかりやすい部分にできやすく、放置すると痛みが悪化することもあります。魚の目はタコに似ていますが、タコと違って芯があるため、強い痛みを伴うことも。自己処理を考える方も多いかもしれませんが、この芯を取り除かなければ改善できないので、自分で対処するのはあまりおすすめできません。
魚の目ができる原因は?
魚の目は、皮膚の一部に継続して刺激や圧力がかかることで発生します。以下の状況が続くと魚の目ができやすくなるといわれています。
- サイズの合わない靴を履き続ける
- 長時間歩く
特定の部位に過剰な負担がかかることで、皮膚が自らを守るために角質を厚くしようとします。この防御反応が続くと、硬くなった角質が皮膚の内側へと食い込み、芯を持った魚の目となるのです。
皮膚のすぐ下に骨がある部分は、圧力の逃げ場がなく、より魚の目ができやすいといわれています。足の指の関節や裏側にできやすいのはこのためです。
また、外反母趾や扁平足、O脚など足の形状に特徴が出る症状の場合、特定の部分に圧力がかかりやすくなるため、魚の目を発症する原因となることがあります。
魚の目は自己処理で改善できる?
魚の目ができると、つい自分で削りたくなるかもしれません。しかし、自己処理には注意が必要です。魚の目には芯があり、表面だけを削っても芯が残ったままだと痛みが続いてしまいます。また、無理に削ると皮膚を傷つけ、炎症や感染のリスクを高めることもあります。
市販の角質ケア用品を使う方法もありますが、芯が深い場合は根本的な改善にはつながらないことがほとんどです。安全に治すためには、専門の医療機関で治療を受けるのがおすすめです。また、魚の目ができる原因を見直して、靴や歩き方を改善することも大切です。無理に削るよりも、正しいケアを心がけましょう。
魚の目をケアする方法は?
魚の目ができてしまったら、できるだけ早めにケアすることが大切です。放置すると、歩くたびに痛みを感じるようになったり、さらには悪化したりすることもあります。ケアの方法はいくつかありますが、絆創膏で保護することや、塗り薬を塗るなどの方法がおすすめです。
絆創膏によるケアは、魚の目を保護しながら少しずつ改善を促します。一方で、目立たせたくない場合は、塗り薬タイプの治療薬を活用するのも良い方法です。どちらを選ぶかは、魚の目ができた場所や、生活スタイルに合わせて決めるとよいでしょう。ここからは、ケア方法について具体的にご紹介します。
絆創膏で保護する
歩くときに痛みを感じたり、こすれて違和感を覚える場合は、絆創膏で保護しましょう。もし売っていれば、魚の目用パッドがおすすめです。薬剤がついた部分とクッション性のある保護パッドが一体になっているものが多く、患部を保護できます。
また、魚の目ができた場所によってぴったりな形状は異なるため、指にフィットするものや足裏用のものなど、現在の症状に合ったタイプを選ぶのがポイントです。もし、ぴったり合うものが見つからない場合は、自分でカットして使えるものを選ぶのも良いでしょう。
塗り薬を塗る
魚の目を目立たせずにケアしたい場合は、塗り薬タイプの薬を使うのもおすすめです。特に、サンダルを履く季節や裸足になる機会が多いときは、絆創膏を貼るのに抵抗があることもありますよね。そんなときは、透明な塗り薬を使うことで、外見に影響を与えずに保護することができます。
塗り薬は、乾くと皮膚に膜をつくり、魚の目を保護しながら少しずつ角質を柔らかくしていきます。ただし、絆創膏タイプと異なり、毎日こまめに塗り直す必要があるため、継続して使うことが大切です。また、一部の塗り薬には保護パッドが付属しているものもありますが、多少目立つことがあるため、使用する際はその点も考慮しましょう。
魚の目を放っておくとどうなる?
魚の目は小さくても痛みを伴うことが多く、放置するとさらに悪化する可能性があります。初めは軽い違和感だけだったものが、時間とともに角質が厚くなり、痛みが増していくことがあります。歩行時に負担がかかる部分にできた場合は、歩くのが特につらくなってしまうことも。
また、皮膚の硬化が進むと、細菌が入りやすくなり、感染症を引き起こすこともあります。さらに、痛みを避けようとして不自然な歩き方になることで、足や体全体のバランスが崩れることが懸念されます。悪化を防ぐためにも、早めにケアをすることが大切です。
痛みが悪化する
魚の目を放置すると、皮膚の角質がさらに厚くなり、芯も深くなってしまいます。その結果、歩くたびに強い痛みを感じるようになり、靴を履くだけでもつらくなることがあります。特に、長時間歩いたり立ち仕事をしていたりすると、症状が悪化しやすいことに注意が必要です。
さらに、見た目の変化も気になるようになります。初めは小さかった魚の目が広がり、表面が硬くゴツゴツとした状態になってしまうこともあります。日常生活の中で常に痛みを感じるようになる前にケアしていくことが大切です。
感染のリスクが高まる
魚の目を長期間放置すると、皮膚の硬くなった部分がひび割れてしまうことがあります。その隙間から細菌が入り込むと、炎症を起こして赤く腫れたり、膿がたまったりすることも。免疫力が低下していると、感染症が広がるリスクも高まります。
感染が進むと、痛みがさらにひどくなり、歩くのも困難になることがあります。場合によっては、医療機関での治療が必要になることも。魚の目が硬くなりすぎる前に、ケアを行って、清潔な状態を保つことを意識してくださいね。
歩きにくくなる
魚の目が大きくなり痛みが強くなると、無意識のうちに痛みを避けるような歩き方をしてしまいます。例えば、片足に重心をかけたり、つま先歩きをすることで、足のバランスが崩れてしまうことがあります。その結果、膝や腰に負担がかかり、別の部位にも痛みが出ることも。
また、歩行が制限されると、足の筋力が低下し、転倒のリスクが高まります。特に高齢者の場合、転倒によるケガが大きな問題となることもあるため、魚の目を見つけたら放置しないようにしましょう。
当院で行う魚の目の改善方法は?
魚の目を改善するためには、まず痛みの原因となる芯をしっかり取り除くことが大切です。一般的な皮膚科では、液体窒素を使って冷却し、魚の目を取り除く治療が行われることがありますが、これは本来ウイルス性のイボの治療に使われる方法であり、強い痛みを伴うこともあります。また、完全に魚の目を除去できない場合もあるため、治療後に再発することもあります。
当院では、特殊な技術を用いて皮膚を柔らかくし、芯が取りやすい状態に整えてから、丁寧に削る方法を採用しています。痛みを抑えながら、なめらかで自然な仕上がりになるようにケアを行うため、見た目もきれいに改善されるのが特徴です。
広島周辺で魚の目でお悩みの方はセラピストプラネットにご相談ください!
この記事では、魚の目ができる原因やケア方法などについて詳しくご紹介しました。魚の目を見つけたら自己処理したくなる気持ちはわかりますが、かえって痛みがひどくなったり、炎症を起こしたりする可能性があるため、そんな時は、当院にお任せください。
セラピストプラネットでは、巻き爪施術をはじめとする専門資格を持った先生が各院に在籍しています。
もし現在、広島周辺で魚の目でお悩みの方はセラピストプラネットにお気軽にご相談ください!