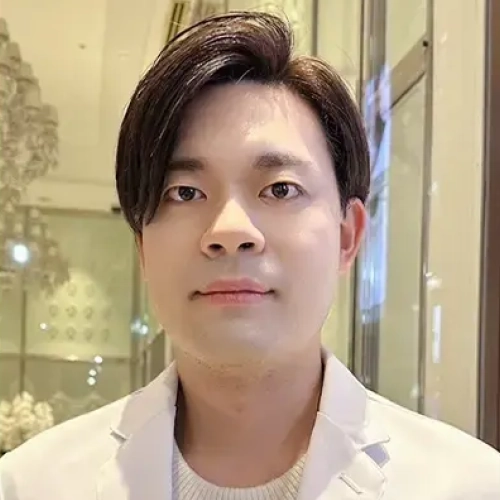足の巻き爪の治し方は?自分でできる方法&予防方法などを解説!

足の巻き爪は悪化すると痛みを感じることがあるため、不快に感じている方は多いでしょう。足の爪が巻き爪になった時は、ぜひ自分でできるケアをお試しください。この記事では、足の爪の巻き爪を改善するために自分でできるケア方法や、予防方法などについて詳しく解説します。
もくじ
足が巻き爪になる原因は?
巻き爪は、爪の端が内側に巻き込んでしまうことで、痛みや炎症を引き起こすこともあるトラブルです。足の親指に多く見られることが多いですが、その原因は人それぞれ。日常の習慣や足の使い方が関係していることも多く、知らず知らずのうちに巻き爪になりやすい状態を作ってしまっていることもあります。では、どんなことが巻き爪の原因になるのか、詳しくご紹介します。
指の力が弱くなっている
足の爪は本来、歩くときに地面からの圧力を受けながら平らな形を保ちます。
しかし、最近は靴に頼りすぎて足の指をしっかり使わない人が増えているといわれています。例えば、クッション性の高い靴を履いていたり、デスクワークが多く歩く機会が少ないと、足の指に力を入れることが減りがちに。
そうすると、爪がまっすぐ伸びるための適度な刺激がなくなり、少しずつ内側へ巻き込まれてしまいます。
「足の指なんて意識したことがない」という方も多いですが、指をグーパーと動かしたり、地面をしっかり踏みしめて歩く習慣をつけるだけでも違います。普段から意識して、足の指をしっかり使うことが大切です。
足の指に正しく体重がかかっていない
立ち方や歩き方の癖が、巻き爪を引き起こしていることもあります。例えば、無意識のうちにかかとにばかり体重をかけて歩いていたり、足の指をしっかり地面につけずに歩いていると、爪にかかる圧が偏ってしまいます。その結果、爪がうまく成長できず、巻き込まれる形になってしまうことがあるのです。
また、外反母趾などで指の関節が変形している場合も、体重のかかり方がアンバランスになりやすく、爪に余計な負担がかかることがあります。意識的に足の指を使うようにしたり、姿勢を整えることが、巻き爪の予防につながります。
遺伝や骨格によるもの
巻き爪は、後天的なものだけでなく、生まれ持った足の形が関係していることがあります。
もともと爪の形が丸みを帯びている人や、足の骨格の影響で指に力が入りにくい人は、巻き爪になりやすい傾向があります。
また、家族に巻き爪の人が多い場合、同じような足の形や歩き方の癖を受け継いでいることも。こうした場合は、早めに対策をとることが大切です。自分に合った靴を選んだり、足の指をしっかり動かす習慣をつけるだけでも、巻き爪のリスクを減らすことができます。
足の巻き爪を予防する方法は?
巻き爪は、一度なってしまうと痛みや炎症が起こることもあり、歩くのがつらくなってしまいます。日常生活の中で気をつけることで、巻き爪を防ぐことができるので、ぜひ取り入れてみてください。爪の切り方や歩き方は、巻き爪の予防にとても大切なポイントです。
正しい爪の切り方を身につける
爪を短く切りすぎると、歩いたときに皮膚に食い込みやすくなります。とはいえ、長く伸ばしすぎると、爪がどんどん内側に巻いてしまうことも。巻き爪を防ぐためには、ちょうどいい長さを保つことが大切です。目安としては、爪の先に白い部分が少し残るくらいがちょうどいいでしょう。
また、爪を切るときは、深く切り込まずにスクエア型(まっすぐな形)を意識すると、爪が変形しにくくなります。爪切りだけで巻き爪を治すことは難しいですが、爪の切り方を意識することで、悪化を防ぐことができます。
歩き方に注意する
正しい歩き方を意識することも、巻き爪の予防につながります。歩くときに、足の指がしっかり地面につくように意識すると、爪に適度な刺激が加わり、巻き爪を防ぎやすくなります。逆に、かかとばかりに重心がかかる歩き方をしていると、足の指をうまく使えず、巻き爪のリスクが高まってしまいます。
また、靴のサイズや履き方にも注意が必要です。小さすぎる靴は足を圧迫してしまい、爪が変形しやすくなります。反対に、大きすぎる靴は足が中で動いてしまい、爪に余計な負担がかかることも。靴を選ぶときは、足にフィットするサイズを選び、ひも靴の場合はしっかりとひもを締めて足を固定するのがおすすめです。正しい歩き方と適切な靴選びを意識することで、巻き爪を予防しやすくなりますよ。
爪にコットンを挟む
上記2つの方法で、巻き爪を予防することができます。もしすでに巻き爪になっている場合でも、軽度であれば悪化を予防することが可能です。簡単な方法のひとつが、爪にコットンを挟むことです。
巻き込んだ爪の先端に小さく丸めたコットンをそっと差し込むと、爪が皮膚に食い込むのを防ぎ、痛みを和らげることができます。入れる量は少しずつ調整し、無理に押し込まないように注意しましょう。
巻き爪と陥入爪の違いは?
巻き爪と陥入爪(かんにゅうそう)は、どちらも爪のトラブルですが、実は違うものです。見た目が似ているため混同されがちですが、それぞれ特徴や原因が異なります。ここでは、その違いについてご紹介します。
まず巻き爪とは、爪の端が内側に丸く巻き込んでしまう状態です。爪が徐々に変形し、両側が弧を描くように曲がってくるのが特徴です。巻き爪の主な原因には、足の指をしっかり使えていないことや、靴の圧迫、爪の切り方の間違いなどが挙げられます。巻き爪自体は必ずしも痛みを伴うわけではありませんが、進行すると指の皮膚を圧迫し、違和感や痛みが出ることもあります。
一方で陥入爪は、爪の角や先端が皮膚に食い込み、炎症を起こしている状態のことをいいます。爪が周囲の皮膚を傷つけることで、赤く腫れたり、痛みを感じたりすることがほとんどです。炎症がひどくなると、膿がたまることもあります。陥入爪は、深爪や爪の切り方のミスが原因で起こることが多く、特に爪の角を丸く切りすぎると、爪が伸びたときに皮膚へ食い込みやすくなります。
巻き爪と陥入爪は、別々の状態ではありますが、両方が同時に起こることもあります。例えば、巻き爪が進行して爪が強く巻き込むと、その先端が皮膚に食い込み、陥入爪を引き起こすことも。このような場合、爪の形を整えるだけでなく、炎症を抑える対処も必要です。
巻き爪は何の栄養が不足している?
巻き爪は、爪が健康に育たないことで悪化しやすくなります。特にタンパク質・ビタミン・ミネラルが不足すると、爪が弱くなり巻き爪のリスクが高まるため、意識的に摂取してみましょう。
タンパク質(爪の主成分)
爪の主成分であるケラチンはタンパク質の一種。これが不足すると、爪がもろくなり巻き爪になりやすくなります。
- 動物性タンパク質(肉・魚・卵・乳製品):爪を丈夫にする
- 植物性タンパク質(大豆・豆類):爪に弾力を与える
ビタミン(爪の成長を助ける)
- ビタミンA(レバー・ほうれん草):爪の形成を助ける
- ビタミンB2(うなぎ・乳製品):丈夫な爪を作る
- ビタミンE(ナッツ・アボカド):血流を促し、健康な爪を維持
ミネラル(爪の変形を防ぐ)
- 鉄分(レバー・まぐろ・小松菜):爪の血行を促し、変形を防ぐ
巻き爪を予防するには、栄養バランスの良い食事を心がけることが大切です。
広島周辺で足の巻き爪にお悩みの方はセラピストプラネットにご相談ください!
この記事では、足の巻き爪を自分で改善する方法などについて詳しくご紹介しました。
症状が悪化すると痛みを感じることがあるので、ぜひこの記事でご紹介した方法をできる範囲でお試しください。
セラピストプラネットでは、巻き爪施術をはじめとする専門資格を持った先生が各院に在籍しています。
もし現在、広島周辺で足の巻き爪でお悩みの方はセラピストプラネットにお気軽にご相談ください!