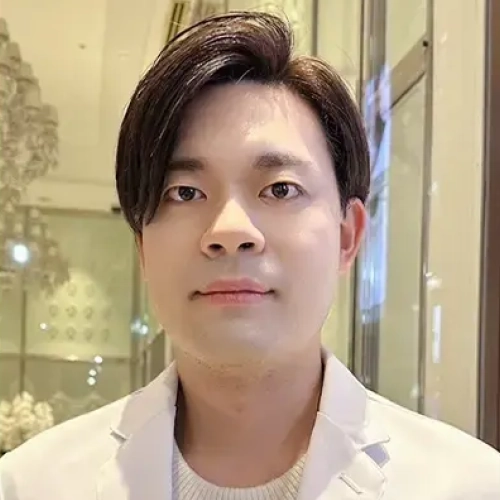足の固いまめができる原因は?とる方法や予防方法について解説!

足に固いまめができると痛みを感じたり違和感を覚えたりすることがあります。まめをとる方法はさまざまですが、市販薬を使って自分でとることが可能です。しかし、固すぎてとれない場合や痛みが強い場合は病院などに相談してくださいね。この記事では、足の固いまめができる原因や、まめをとる方法、予防方法などについて詳しくご紹介します。
もくじ
足にできる「まめ」とは?
足にできる「まめ」とは、皮膚の一部分が摩擦や圧迫を繰り返して受けることでできる水ぶくれや角質の塊のことです。長時間歩いたり、新しい靴を履いたりすると、特定の場所に強い負担がかかって皮膚の表面がダメージを受けることで発生します。
まめには大きく分けて2種類あります。
一つは、水ぶくれのような「摩擦まめ」で、初期の段階では透明な液体が溜まっており、痛みを伴うことがほとんどです。もう一つは、皮膚が硬く厚くなる「胼胝(たこ)」や「鶏眼(魚の目)」と呼ばれるものです。これらは、摩擦や圧迫が継続的にかかることによって角質が厚くなり、放置すると痛みを伴います。
足に固いまめができる原因は?
足に固いまめができる主な原因は、皮膚への摩擦や圧迫です。ランニングやマラソンなど、長時間足を使う運動では、足の裏や指が靴の中でこすれるため、特に負担がかかります。
歩くたびに足は地面からの衝撃を受けていますが、ランニングや長時間の歩行ではその負担が何倍にも増します。その結果、皮膚の表面(表皮)とその下の層(真皮)が擦れてダメージを受け、火傷のように赤くなることがあります。このとき、皮膚の隙間に体液がたまることで水ぶくれとなり、摩擦が続くと固い角質へと変化するのです。
また、サイズの合わない靴や硬い靴底の靴を履いていると、特定の部位に圧力がかかりやすく、よりまめができやすくなります。
ひどい場合には、水ぶくれが破れたり、出血を伴うこともあるため、ケアが大切です。
足の固いまめは自然治癒できる?
「まめができるのはよくあることだから」と、そのまま放置してしまう方もいるかもしれません。確かに、痛みが少ない場合や軽度なものであれば、自然に改善していくこともあります。しかし、何もせずに放っておくと、摩擦や圧迫が続いて角質がさらに硬くなったり、ひび割れて痛みを伴うことがあります。そのため、自然治癒を狙うのはあまりおすすめできません。
また、傷口が開いてしまった場合には、雑菌が入り込む可能性があり、炎症を起こして化膿することも。足は汗をかきやすく靴の中で蒸れやすいため、細菌が繁殖しやすい環境になりがちです。
そのため、まめができたら放置せずに早めに対処することが大切です。スピール膏や角質軟化剤を活用してケアしたり、テーピングで摩擦を防ぐなどの対策を取りましょう。
足の固いまめをとる方法は?
歩くたびに痛みを感じる足の固いまめは、とても気になるものです。放置しているとどんどん厚くなり、さらに取りにくくなることも。そこで、自宅でできるセルフケアの方法をご紹介します。市販の薬を使ったり角質を柔らかくする方法を試したりすることで、少しずつ改善を目指しましょう。
スピール膏貼付
皮膚が硬くなり、厚くなってしまった場合には、スピール膏と呼ばれるサリチル酸を含んだ貼り薬を使います。スピール膏には、絆創膏タイプ、液体タイプ、ジェルタイプなどさまざまな種類があり、その中から症状に合った使いやすいものを選びます。
使い方は、患部の大きさに合わせてスピール膏をカットし、まめの部分に貼り、その上から絆創膏などで固定。2〜3日ほど貼り続けると角質が白くふやけてくるので、そのタイミングで新しいものと交換します。白くなった角質は、自然に取れるのを待つか、ピンセットなどを使って取り除きます。
もし中心部分にまだ硬い芯が残っている場合は、もうしばらくスピール膏を貼り続けることで、少しずつ改善していきます。
角質軟化剤
まだそれほど硬くなっていないまめや魚の目の場合は、角質を柔らかくするクリームや軟膏を使うことが一般的です。ケラチナミン軟膏やサリチル酸を含んだ軟膏を塗ることで、皮膚を柔らかくし、少しずつ自然に削りやすくすることができます。
入浴後など皮膚が水分を含んでふやけたタイミングで使うのが、よりおすすめです。薬を塗った後、やわらかくなった部分を軽石などで優しくこすることで、無理なく除去することができます。削りすぎると皮膚を傷めてしまうため、少しずつ行うことが大切です。
鶏眼・胼胝処置
もし、セルフケアで改善しない場合や、痛みが強い場合は、皮膚科などでの処置を検討しましょう。皮膚科などの専門機関では、「ペディ=コーンカッター」と呼ばれる専用の器具を使って、硬くなった角質を少しずつ削る処置を行います。
この方法は比較的安全に角質を除去できるため、よく取り入れられています。自己処理でなかなか改善しない場合や、まめが深くなってしまった場合は、無理に削らずに当院にご相談ください。病院よりも丁寧で解決が早いのが特徴で、多くの方に満足いただいております。ぜひお気軽にお問い合わせください。
足のまめを予防する方法は?
足のまめは、一度できると痛みを伴うことが多く、歩くのが辛くなってしまうこともあります。だからこそ、できる前にしっかり予防することが大切です。靴の選び方や靴下の工夫、テーピングの活用などの方法でまめを防いでいきましょう。具体的な方法を3つご紹介します。
通気性の良い靴を履く
靴の中が蒸れると、足の皮膚がふやけて柔らかくなり、摩擦によるダメージを受けやすくなります。そのため、通気性の良い靴を選ぶことが大切です。
ランニングシューズにはメッシュ素材を使用したものが多く、靴内の湿気を逃がしやすい作りになっています。最近では、靴底やインソールに通気孔があるモデルもあり、より快適に履くことが可能です。日常用の靴でも、通気性に優れた素材のものを選べば、まめができにくくなります。
5本指ソックスを着用する
足の指同士が直接擦れ合うことで、まめができることがあります。その対策として、5本指ソックスを履くのがおすすめです。指ごとに布地で覆われるため、摩擦が軽減され、指の間の蒸れも防ぐことができます。
また、5本指ソックスを履くことで足指が自由に動かせるようになり、歩行時のバランスが良くなるのもメリットです。最初は違和感を覚えることもありますが、少しずつ慣れることで違和感なく履けるようになります。さらに、滑り止め付きのものを選べば、靴の中で足がズレるのを防ぎ、よりまめができにくくなります。
テーピングを活用する
同じ場所に繰り返しまめができる場合は、テーピングを活用するのも良い方法です。テープを貼ることで、皮膚への摩擦を減らし、負担を和らげることができます。
テーピングの方法としては、まず足の裏に縦と横にテープを貼り、端を足の甲まで巻き込むようにするとしっかり固定されます。さらに、足の指にもテープを巻くと、摩擦を軽減できます。
また、テーピングをする時には、伸縮性のあるものを軽く貼ることで動きやすさを損なわず、快適に過ごせるため、長時間歩く予定のあるときや新しい靴を履くときに試してみてください。
広島周辺で足のまめにお悩みの方はセラピストプラネットにご相談ください!
この記事では、足のまめが固い原因やまめをとる方法、予防方法などについて詳しくご紹介しました。足にまめができると痛みを伴うことが多いので、特定の部分が固い気がしたら放置せずに病院などに相談するようにしましょう。
セラピストプラネットでは、巻き爪施術をはじめとする専門資格を持った先生が各院に在籍しています。
もし現在、広島周辺で足のまめにお悩みの方はセラピストプラネットにお気軽にご相談ください!